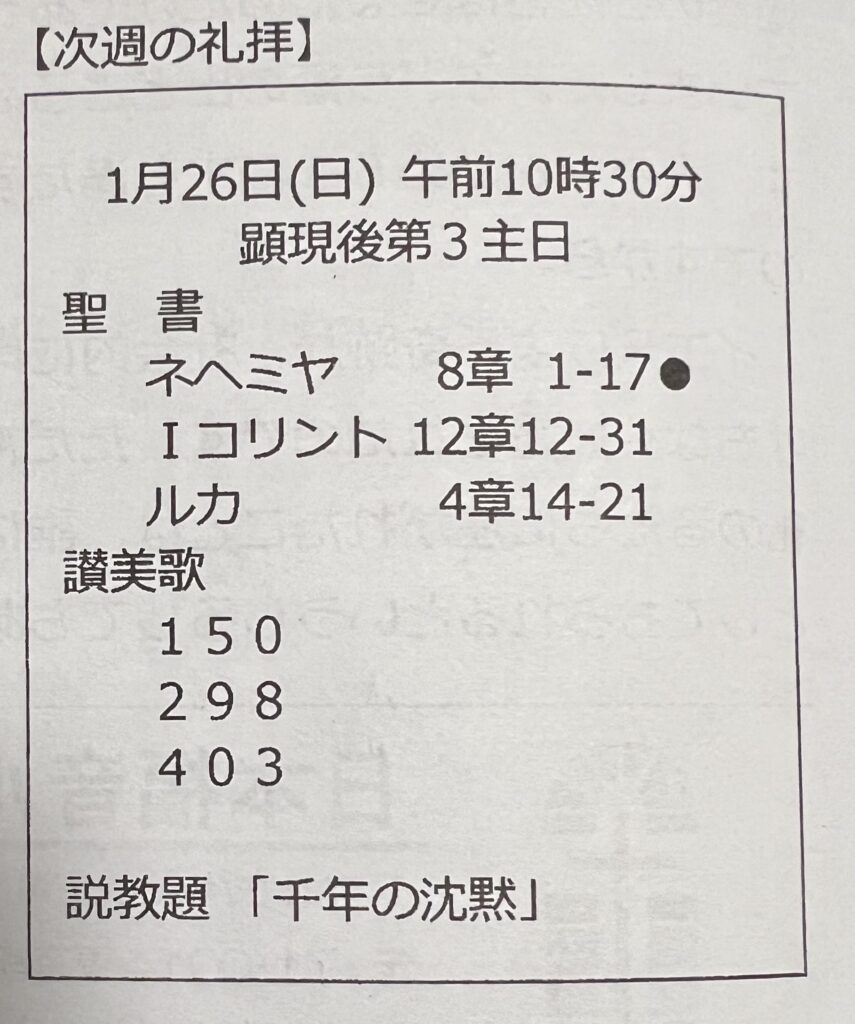2025.1.19説教「満たす」
顕現後第2主日
「満たす」
ヨハネ2章1-11
2:1 三日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。
2:2 イエスも、その弟子たちも婚礼に招かれた。
2:3 ぶどう酒が足りなくなったので、母がイエスに、「ぶどう酒がなくなりました」と言った。
2:4 イエスは母に言われた。「婦人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。わたしの時はまだ来ていません。」
2:5 しかし、母は召し使いたちに、「この人が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」と言った。
2:6 そこには、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめが六つ置いてあった。いずれも二ないし三メトレテス入りのものである。
2:7 イエスが、「水がめに水をいっぱい入れなさい」と言われると、召し使いたちは、かめの縁まで水を満たした。
2:8 イエスは、「さあ、それをくんで宴会の世話役のところへ持って行きなさい」と言われた。召し使いたちは運んで行った。
2:9 世話役はぶどう酒に変わった水の味見をした。このぶどう酒がどこから来たのか、水をくんだ召し使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで、
2:10 言った。「だれでも初めに良いぶどう酒を出し、酔いがまわったころに劣ったものを出すものですが、あなたは良いぶどう酒を今まで取って置かれました。」
2:11 イエスは、この最初のしるしをガリラヤのカナで行って、その栄光を現された。それで、弟子たちはイエスを信じた。
「私たちの神と主イエス・キリストから、恵みと平安とがあなたがたにあるように。」
本日の御言葉は、ヨハネによる福音書の2章。著者ヨハネが伝える、イエスによる最初の奇跡物語です。
初めに、聖書に収められている「福音書」の成り立ちについて、改めてご説明致します。
ヨハネによる福音書が書かれたのは西暦100年頃と考えられています。そして、ヨハネ福音書は聖書に収められている4つの福音書の中で最後に書かれた福音書です。
最初に書かれた福音書はマルコによる福音書。西暦70年頃のことでした。歴史的には、ユダヤの中心であるエルサレム神殿がローマ軍によって破壊された頃でありました。ユダヤ人の歴史と信仰のシンボルであり、ユダヤ教においては罪の赦しをいただくために生贄を捧げる場であった神殿を、ユダヤの人々は喪ったのです。
絶望的とも言える喪失感の中で、ユダヤ教にあらずキリスト教とは言え、御言葉の神殿とも言える福音書が世に出されたのですから、多くの人々の拠り所となったことは間違いありません。また、マルコによる福音書は、初めての福音書としてキリストの生涯を世界に向かって告げ知らせたのです。
マルコ福音書に遅れること10年、マタイによる福音書とルカによる福音書が書かれました。マタイ福音書はユダヤ教徒にユダヤ教の成就としてのキリスト教を伝えるために書かれました。ルカによる福音書は、社会的に弱い立場の人のために書かれました。「弱い立場の人々」とは、貧しい人、病気の人や障がいのある人、女性や子ども、ユダヤに寄留している外国人たちのことです。
福音書を書くにあたって、著者たちはイエスに関する多くの情報を収集し、それぞれの視点から情報を取捨選択することによって編集されたものが、福音書と言う「キリストの生涯物語」です。
ですから、最後の福音書を書くにあたって、著者ヨハネは他の福音書の著者たちの誰よりも多くの情報を持っていたことになります。
その数ある情報の中からヨハネが選択した最初の奇跡物語が、本日読んでおります、「カナの婚礼」と呼ばれる出来事なのです。これはヨハネだけが伝える出来事でもあります。
私たちも、少し聖書に親しんだり、長く教会での生活をすることによって、イエスに関するたくさんの情報を持っています。それに、自分自身の信仰体験や信仰の友による証言までも加わっています。知識の量からすれば、大層豊かな状態であると言えましょう。
では、私たちならば、あなたならば、イエスについて最初に隣人に伝えたいこととして、どの出来事を選ぶのでしょうか?
本日の箇所である、著者ヨハネが選んだ「水がぶどう酒に変わる」だけの奇跡物語は、イエスによって誰かの罪が赦されるわけでなく、死者が復活するわけでもなく、聖書的には平凡です。ここで著者ヨハネが伝えようとしたメッセージは何であったのでしょうか。
シンプルな出来事ではありますが、きちんとストーリーをご存じではない方もおられますので、順にたどってまいりましょう。
場所は、どこであったのかを見ますと、少し前のヨハネ福音書1章28節に、「べタニア」という地名が出ていました。そこは、ヨルダン川が死海に流れ込むあたりに遠くない土地でありました。
29節に「その翌日」とあり、35節にも「その翌日」とあり、さらに43節にも「その翌日」とあります。
そして、ようやく2章1節で「三日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって」と、本日の箇所へと続きます。
べタニアからカナまでは、それほどの道のりがあったことや、距離と時間を描く編集者の苦労がうかがえるところです。
この「カナの婚礼」と呼ばれる出来事は、ヨハネ福音書だけが伝えている話ではありますが、舞台が「ガリラヤ」であるという話の背景は、実はこの話がユダヤの伝承として古くから伝えられてきたものの一つであるということを証ししています。
著者ヨハネが創作した逸話というわけではないのです。
2節、イエスと弟子たちは、カナでの婚礼へと招かれました。そして、その婚礼には、どういういきさつか、イエスの母・マリアがいたのです。しかも、ただの参列者ではなく、ぶどう酒が足りないことを心配する、宴会の世話係を担っていたようです。
聖書には「婚礼」のたとえが幾つか書かれておりますが、マタイによる福音書22章には、イエスによるたとえ話として、ある王が王子のために婚宴を開催する様子が語られています。その話の中で、招待客が来ないので、王は家来たちを大通りに行かせて、通行人を連れて来させる話があります。
たとえにしても「まさか」と思うことですが、実際、外国旅行中に見知らぬ人の婚宴に招かれるという体験をしたことがありました。
韓国では、ある教会を訪問した時に、ちょうど結婚式が行われていたのですが、私たち旅行者も「クリスチャンだから」と理由で、婚宴の席に招かれました。
もう一つの体験は、タイでのことでした。通りがかりに教会を見つけ、何やら賑やかだったので様子を見ておりましたら、「まあ、いいから入れ」とばかりに、まったく見知らぬ人々の婚宴の席に招かれたのでした。所変わればの婚宴の様子でありました。
さて、本日の婚宴の話は、3節でいきなり本題へと入ります。《ぶどう酒が足りなくなったので、母がイエスに、ぶどう酒がなくなりました」と言った。》とあります。
マリアからイエスへの願いにも驚かされますが、話の展開のあまりの稚拙さに抵抗感さえ感じます。
すると、4節でイエスが母マリアへと答えておられます。
「婦人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。わたしの時はまだ来ていません。」
イエスの当然の答えに納得させられます。
「わたしの時はまだ来ていません。」
イエスは決して人の事情によらず、場の求めによらず、神の御旨にのみ立つことを、著者ヨハネはこの一言で示しています。もっともな示唆です。
では、イエスの「わたしの時」とは何かと問えば、イエスにとっては神が定められた時であり、十字架に上がることで神の御旨が成就されること、そして、神のもとへ返って栄光を受ける時であることが、のちにヨハネ福音書を通して知らされることになります。
確かに、人となられた神の子だけが、人間の無力さというものを終わらせることは出来ますが、けれども、そのような神からの助けは人間が要求できるものではないことは明らかです。それは神の意志によるのであり、神ご自身が果たされることなのです。
ところが、マリアは、イエスが奇跡を起こす力を、たとえ婚宴の客を喜ばせるためだけであっても、発揮してくれるであろうことを確信しているのです。
5節、《しかし、母は召し使いたちに、「この人が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」と言った。》
そして、召し使いたちはイエスが「そのような方」であることを、マリアに次いで予期するに至るのです。
神には神の予定があります。
人々の都合で変えられるものではありません。
しかし、神の予定は絶対変わらない、不動のものであるかと言えば、そうでもないのです。
神は確かに予定を持っておられます。しかし、神ご自身が欲したもうところによって、その予定が早められることがあるということもまた聖書は証言しています。
そこで、イエスが「水をぶどう酒に変える」という奇跡を目撃した者は誰であったのかを見てみましょう。
奇跡の目撃者は、イエスの世の母であるマリアではなく、イエスの弟子たちでもなく、ましてや婚礼の主役たちでも世話役でもありませんでした。彼らは宴会に忙しく、舞台裏を知る由もなかったのです。
ぶどう酒の出どころを知っているのは、召し使いたちだけでした。大きな水がめ6つに水を満たすという労働をしたのは、彼ら自身であったのですから。
この「6つの水がめ」について、著者ヨハネは説明を付けています。6節、《そこには、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめが六つ置いてあった。いずれも二ないし三メトレテス入りのものである。》とあります。
ただの水がめではなく、「ユダヤ人が清めに用いる石の水がめ」であったことと、6つで700リットルもの容量であるということが説明されています。
ユダヤ人にとっての「清め」の定めは、モーセ以来のものであり、1500年にわたるイスラエルの慣習でありました。
来客を迎えた時のおもてなしとしての「清め」、食事前の「清め」、礼拝する時の「清め」など、生活全般に「清め」の儀式があり、そのための水が必要とされていました。
ここには、ユダヤの伝統があり、また新たに著者ヨハネにとってのキリストの使命が隠されていることと思われます。この「清め」については、また別の機会に取り上げることに致します。
イエスによる奇跡が、
ヨハネ福音書で紹介される初めての奇跡物語が、
社会的には小さき者とされている召使たちに、まず、惜しげもなく披露され、驚きで満たされたのです。
このイエスによる奇跡の出来事には、人が成し得ることではなく、人の力が入り込む余地のない出来事でありました。
召し使いにより世話役へと試飲のためのぶどう酒が運ばれ、事態は明るみに出されます。裏舞台の事情が表舞台へと現れ、世話役の花婿への感嘆と称賛を通して、マリアと弟子たちもまた、事の真相を知らされたのです。
「それで、弟子たちはイエスを信じた。」と出来事は締めくくられています。
弟子たちの役割の重要性は、「奇跡を見たところにではなく、召し使いたちの証言を信じた」という点にあるように思います。
イエスによる奇跡は、人の事情によらず、場の求めによらず、神の御心によってのみ起こるものです。
ただ神のみの意志による祝福が、聖書に名も記されぬ者たちに満たされたことは、誰にでも、私たちにも、神は心を動かす方としておられるというしるしでもあるのです。
この新たな一年も、そのように、神の御心は成就するであろうし、神の御心しか成らんと信じます。
「望みの神が、信仰からくるあらゆる喜びと平安とをあなたがたに満たし、聖霊の力によって、あなたがたを望みに溢れさせてくださいます。」